「ブロックチェーンって、管理者がいないから安全なんでしょ?
実はこれ、半分正しくて、半分間違いなんです。
この記事では「ブロックチェーン=管理者なし」というイメージを見直しながら、わかりやすくブロックチェーンの基本と種類を紹介していきます。
ブロックチェーンとは?
まず、ブロックチェーンとは、データを鎖(チェーン)のように繋げることで改ざんを防ぎ、複数の機器(ノード)で共有・保存する技術のことです。
もう少し砕いて言えば、
「一度書いたデータが消せない、みんなで管理する“共有の台帳”」
とも言えるかもしれません。
「ブロックチェーンって、よく分からない…」という方へ
「ブロックチェーンって聞いたことあるけど、正直よく分からない…」
そんな方には、このイメージだけで十分です。
なぜなら、実際にブロックチェーンを本気で理解しようとすると、かなり奥が深く、専門的です。
ブロックチェーンの専門的な定義
とはいえ、「イメージだけじゃ物足りない!」という方のために、少し専門的な定義も紹介しておきます。
日本ブロックチェーン協会では、ブロックチェーンを次のように定義しています:
1. ビザンチン障害を含む不特定多数のノードを用い、時間の経過とともにその時点の合意が覆る確率が0へ収束するプロトコル、またはその実装をブロックチェーンと呼ぶ。
2. 電子署名とハッシュポインタを使用し改ざん検出が容易なデータ構造を持ち、かつ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性およびデータ同一性等を実現する技術を広義のブロックチェーンと呼ぶ。
聞いたことない用語ばかりでめちゃめちゃ難しくないですか?
この定義を理解しようとなるとかなり勉強が必要になります。
なので、「ブロックチェーンって聞いたことあるけど、正直よく分からない…」
そんな方には、イメージだけで十分です。
なぜなら私は、今後はインターネットと同じように、「仕組みを知らなくても使う」ことが当たり前になっていくと感じています。
インターネットも仕組みは知らずに使っている
例えば、インターネットについてどう説明できますか?
私はせいぜい、
「世界中のコンピューターやスマホなどの機械がつながって、情報のやり取りができる仕組みのこと」
くらいしか言えません。
それでもYouTubeを見たり、LINEで連絡を取ったり、こうしてブログ記事を書いたりしています。
なので、わざわざ難しい専門用語まで理解する必要はありません。
「ブロックチェーン=管理者なし」はちょっと違う?
「でも結局、ブロックチェーンって“管理者がいない技術”ってことでしょ?」
そう思った方に、いよいよ本題です。
その認識は大きく間違ってはいませんが、ブロックチェーン全体の定義としては不完全です。
実はブロックチェーンには、**「どのくらい分散されているか」**によって、大きく3つの種類があります。
中央管理者がいないのは、その中の一つである「パブリック型」です(ビットコインやイーサリアムなど)。
ブロックチェーンの主な3種類(代表例つき)
完全に分散された「パブリック型」
例:ビットコイン(Bitcoin)/イーサリアム(Ethereum)/ソラナ(Solana)
複数の組織で運営する「コンソーシアム型」
例:Quorum(J.P. Morgan開発のEthereumベース)/Hyperledger Fabric(IBMなどが支援するDLT基盤)
※Hyperledger Fabricはブロックチェーン構造を持ちつつも、技術的にはより柔軟なDLTとして設計されています。
※Cordaはブロック構造を持たないDLTです。
1社で運営する「プライベート型」
例:企業独自のサプライチェーン管理システム/社内の文書管理用途など
まとめ
このように、ブロックチェーンは一枚岩の仕組みではなく、種類によって性質が異なります。
つまり、すべてのブロックチェーンが「管理者不在」なわけではないんです。
ブロックチェーンには柔軟性があり、使い方や構造によってさまざまな形があります。
最後に
難しいと思っていたけど、なんとなくわかったかも」
そう思ってもらえたら嬉しいです。
それぞれの型やブロックチェーンに関する用語(DLT・ノードなど)も、今後の記事で順に紹介していく予定です。
少しでも興味が湧いた方は、ぜひ次回も読んでいただけたら嬉しいです。
この記事は、新しい記事の内容や気づきを踏まえて、随時アップデートしていきます。
「ブロックチェーンの入り口」として、何度でも戻ってきていただける記事を目指しています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
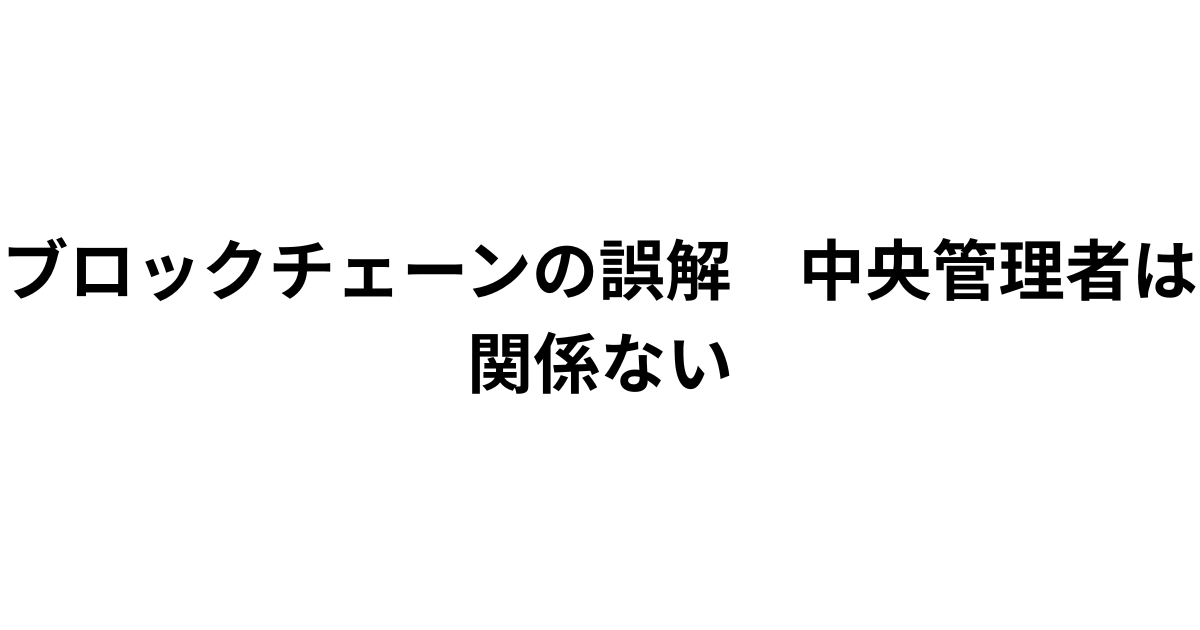
とは?歴史を辿ると見えてくる社会を変える力-120x68.png)
コメント